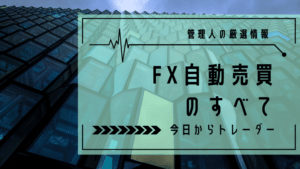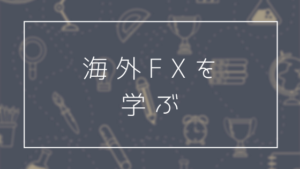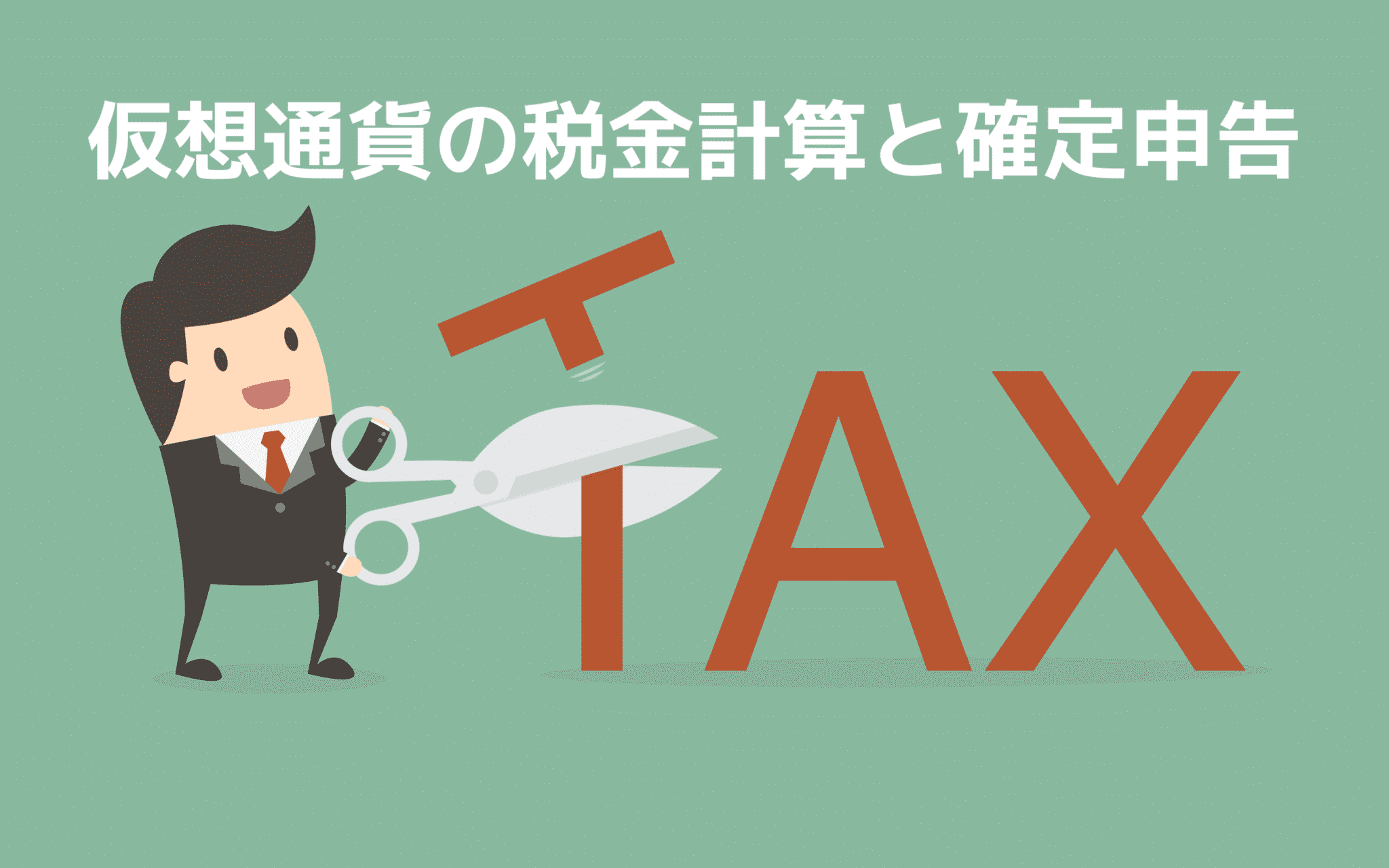

他の仮想通貨初心者の人たちも利益を出すことができたと思うんだ。
だから今回は税金のことを教えてほしいな。

だからこそ、仮想通貨の利益にかかる税金を知っておくことは重要だね。
今回は税金について説明してあげるよ。
2020年後半からビットコインが急上昇したことで、仮想通貨で初めて多くの利益を上げたサラリーマンの人も多いと思います。
「このまま税金を納めなくてもばれないんじゃない?」なんて思っている人がいるかもしれません。
絶対にばれます!国税庁は仮想通貨による利益にかなり鋭く目を光らせています。
「意図していない脱税」によって多額の追徴課税や刑事罰を受けなく済むためにも、税金に関する基本的知識を身につけることは重要です。
そこで今回は、仮想通貨に関する税金の基礎、仮想通貨取引の場面ごとの税計算考え方、サラリーマンの確定申告方法について紹介します。
仮想通貨に関する税金について、かなり網羅的に広く扱っています。
まずは、自分に関係する部分や興味のあるところから読んでみてください。
もし、仮想通貨に関して多額の利益が出ている場合には、今回の記事を参考にしたうえで税理士などの「専門家」に相談することをおすすめします。
目次
- 1 仮想通貨初心者の税金勘違い3選
- 2 サラリーマンのための仮想通貨の税金基礎知識
- 3 仮想通貨「完全網羅」税金計算のケーススタディ
- 3.1 国内取引所を利用した場合の税金計算
- 3.1.1 ケース1:取引所への入金
- 3.1.2 ケース2:日本円での仮想通貨購入
- 3.1.3 ケース3:日本円での購入した仮想通貨の売却
- 3.1.4 ケース4:複数回購入と複数回売却(総平均法)
- 3.1.5 ケース5:複数回購入と複数回売却(移動平均法)
- 3.1.6 総平均法と移動平均法の使い分けについて
- 3.1.7 ケース6:仮想通貨同士の交換
- 3.1.8 ケース7:仮想通貨を自分のウォレットへ送金
- 3.1.9 ケース8:仮想通貨で買い物をした
- 3.1.10 ケース9:仮想通貨を友達にプレゼントした
- 3.1.11 ケース10:仮想通貨をハードフォークによって受け取った
- 3.1.12 ケース11:仮想通貨をエアドロップで受け取った(市場価格なし)
- 3.1.13 ケース12:仮想通貨をエアドロップで受け取った(市場価格あり)
- 3.2 海外取引所を利用した場合の税金計算
- 3.3 仮想通貨FXを利用した場合の税金計算
- 3.4 その他の仮想通貨に関係する税金計算
- 3.1 国内取引所を利用した場合の税金計算
- 4 サラリーマンのための確定申告書の作り方
- 5 サラリーマンの確定申告と税金計算まとめ
仮想通貨初心者の税金勘違い3選

仮想通貨を始めたばかりのころにこんな話を聞いたことはありませんか?
- 仮想通貨にかかる税率は55%もかかる
- 仮想通貨同士の交換では、日本円にしていなければ税金がかからない
- 仮想通貨で買い物をすると税金がかからない
実はこの3つはすべて間違いなんです。
仮想通貨の税率が55%という誤解
仮想通貨の利益にかかる税率は、約20%~55%の間で変動します。
後でも詳しく説明しますが、日本の税制は所得が一定以上を超えるとその分についてだけより高い税率でかける「超過累進税率」を採用しています。
実際に55%の税金がかかるのは、4,000万円を超えて利益が出てる分についてだけです。
2017年後半ごろのビットコインが高騰した際に、「億り人」といわれるような人たちたくさん誕生しました。
彼らの多額の利益にに対して55%の税金を取られる部分が多かったので「仮想通貨の税率は55%」といううわさが広がったのだと思います。
仮想通貨の交換には税率がかからないという誤解
仮想通貨取引で利益が確定するタイミングは、保有している仮想通貨を手放した時です。仮想通貨を日本円に交換した場合は限られません。
なので、ビットコインをアルトコインに交換したタイミングでも利益が確定するので税金がかかってきます。
2017年のビットコイン高騰の際に、ビットコインをアルトコインに交換して利益をまだ確定させないようにともっていた人が多くいました。
しかし、説明した通り、ビットコインをアルトコインに交換したことで、実際には利益が確定してしまっていました。
その結果、彼らは「意図しない脱税」をしてしまっており、追徴課税などを含む多額の納税に苦しむことになってしまいました。
そうならないために、基本的な税金の知識程度は学んでおいて損はありません。
仮想通貨で買い物をすると税金がかからないという誤解
これも仮想通貨の交換と同じように、仮想通貨を手放した時点で利益確定します。
なので、仮想通貨で買い物をしても利益が出ていれば、税金はかかってしまいます。
ただし仮想通貨で購入したものが、仮想通貨取引の必要経費と認められる場合には、経費分を利益から差し引くことができます。
仮想通貨で経費として認められた買い物の額よりも少ない利益しか出ていなかった場合には、税金を取られることはありませんでした。
その結果、仮想通貨で買い物をすると税金がかからないと思う人が増えてしまったようです。
サラリーマンのための仮想通貨の税金基礎知識

サラリーマンの人など、確定申告をしたことがなくて仮想通貨の税金についてよくわかっていない人のために、仮想通貨に関係する税金の基礎知識について紹介していきます。
- 仮想通貨の利益は雑所得になる
- 雑所得は総合課税になる
- 税率は超過累進課税となる
- 損益通算はできないが、内部通算はできる
- 仮想通貨の含み益には課税されない
「いきなり、こんなことを言われても・・・」と思ってしまうかのしれません。
なので、1つずつ順番にわかりやすく解説していきます。
仮想通貨の利益は雑所得になる
仮想通貨取引による所得は雑所得となります。
年間で20万円以上の雑所得がある場合には確定申告が必要となります。
雑所得金額は、以下の方法で計算されます。
「総収入金額-必要経費=雑所得」
「雑所得」=「仮想通貨取引による利益」と考えてほぼ間違いではありません。
- 総収入金額とは、一般的に「仮想通貨の売却金額」のことをに言います。
- 必要経費とは、「仮想通貨の取得原価」や仮想通貨取引に関係する「書籍・PC」などの購入費用が該当します。
ちなみに、仮想通貨の売却金額とは仮想通貨を日本円で売却した場合に限られず、「仮想通貨同士の交換」や「商品やサービスの支払として仮想通貨を利用する」なども含まれます。
仮想通貨の利益(雑所得)は総合課税になる
総合課税とは、給与所得など他の所得と仮想通貨の利益(雑所得)を合わせた金額に税金がかかる仕組みです。
サラリーマンの場合では、給与所得と仮想通貨の利益を合わせた金額が課税の対象となります。
なので、仮想通貨にかかる税金を計算する時には、給与所得と仮想通貨による雑所得を合わせて計算する必要があります。
仮想通貨にかかる税率について
仮想通貨などにかかる所得税は「超過累進税」という性質があります。
超過累進税とは、一定の所得をこえた分について、より高い税率がかかってくるという仕組みです。

計算が複雑なので、国税庁が公表している所得税の速算表を使って計算してみましょう。
仮に年間で仮想通貨の利益が500万出た場合に場合は、500万円×20%-427,500円(速算表の控除額)=572,500円になります。
課税所得330万円までは、20%よりも低い税率がかかり、330万円から500万円までの170万円分には20%の税率がかかります。
実際には500万円に対して、税金が572,500円なので、11.45%の税金がかかったことになります。
その他に所得税に加えて、所得税額の2.1%の復興特別所得税と、一律に約10%の住民税がかかります。
また、サラリーマンは仮想通貨の利益と給与所得を合わせて計算する必要があります。
年末調整を会社でしてもらった後の源泉徴収票を使って、比較的簡単に確定申告をすることができます。
仮想通貨の利益だけでは正確な税金がわかないでの、あくまで目安と思っておきましょう。
損益通算できないが、内部通算はできる
損益通算というのは、不動産所得や事業所得などで損失がでた場合に、その他所得の利益と相殺することです。
仮想通貨は雑所得なので、この損益通算は認められていません。
例えば、仮想通貨で200万円の利益が、不動投資で損失が150万円出ていたとしてして、仮想通貨の200万円の利益にそのまま税金がかかってしまします。
その一方で、内部通算は認められています。
内部通算とは、雑所得などの同じ所得の中で発生した利益と損失を相殺することができるということです。
例えば、ビットコインの取引で200万円の利益を出し、イーサリアムの取引で150万円の損失が出ていた場合には、200万円-150万円=50万円が利益となるということです。
この場合雑所得は50万円になり、50万円分にだけ税金がかかることになります。
損失を翌年以降に繰り越せない
雑所得の特徴として、損失を翌年に繰り越せないというものがあります。
前年の仮想通貨取引で損失が100万円出ていたとしても、翌年の利益と相殺することはできません。
例えば、前年の仮想通貨取引でで100万円の損失が、翌年の仮想通貨取引で200万円の利益がでていたとしても、翌年の200万円の利益にそのまま税金がかかります。
仮想通貨の含み益には課税されない
仮想通貨取引では仮想通貨の「売却時にのみ」課税されます。
仮想通貨の価値が上がっていたとしても、売却しなければ課税されることはありません。
いわゆる「含み益」の状態であっても、その含み益には一切課税がされないのです。
例えば、ビットコインを10万円で購入し、その後に価格が100万円になった場合では、90万円の含み益があります。
仮にこの状態で年を超えたとしても、含み益がその年の課税の対象になることはありません。
仮想通貨「完全網羅」税金計算のケーススタディ

ここでは、実際の仮想通貨取引を踏まえたケースごとの税金計算を説明していきます。
細かく場合分けをし、これを見ればほとんどのケースで所得の計算方法がわかるようになると思います。
難しくなりなりすぎないように、仮想通貨の価格や手数料が実際の取引を異なる場合があるので、その点は気を付けてください。
国内取引所を利用した場合の税金計算
国内取引所を利用した場合の税金計算の方法を紹介します。
ここで紹介するケースは、海外取引所を利用する場合の基礎にもなっています。
よくわかっていない人は、ここを簡単にでも見ておくことをおすすめします。
ケース1:取引所への入金
- 7/1、日本円で100,000円を入金した。その際に振込手数料手数料500円がかかった。
多くの人は取引所への入金に税金は関係ないと思っているかもしれませんが、実は関係があります。
取引所によっては振込手数料がかかることがあり経費として処理することができます。
総収入金額:0円
必要経費:500円
雑所得:0円-500円=▲500円
ケース2:日本円での仮想通貨購入
- 7/10、1BTCを日本円で購入しました。この際に購入手数料が100円かかった。1BTC=10,000円
会計をやったことがない人にとっては、実は仮想通貨の購入は少しややこしいです。
仮想通貨の購入にかかる手数料はそのまま経費になるのではなく、仮想通貨の購入原価に加えます。
つまり、今回購入した1BTCの取得原価は10,000円ではなく10,100円と考えます。
なので、仮想通貨を購入しただけでは、税金の計算には何の影響も与えません。
総収入金額:0円
必要経費:0円
雑所得:0円-0円=0円
ケース3:日本円での購入した仮想通貨の売却
- 7/10、1BTCを日本円で購入しました。この際に購入手数料が100円かかった。1BTC=10,000円
- 7/15、1BTCを日本円で売却しました。この際に売却手数料が150円かかった。1BTC=15,000円
日本円で購入したビットコインが値上がりしたので、売却をして利益が出たケースです。
仮想通貨の取得原価が、ケース2と同様に取得原価が10,100円になります。
売却価格が15,000円となり、取得原価との差額が4,900円となります。
さらにそこから、売却手数料150円を引いた3,750円が利益となります。
総収入金額:15,000円
必要経費:10,000円(購入価格)+100円(購入手数料)+150円(売却手数料)=10,250円
雑所得:15,000円-10,250円=4,750円
ケース4:複数回購入と複数回売却(総平均法)
- 1/1、1BTCを10,000円で購入
- 3/5、2BTCを20,000円で購入
- 5/10、2BTCを40,000円で売却
- 9/15、1BTCを20,000円で購入
- 12/20、1BTCを25,000円で売却
- 12/31、1BTCを30,000円で購入
総平均法とは、1年間の購入金額の累計を取得した仮想通貨数で割り、1通貨当たりの取得原価を計算する方法です。
総平均法で計算した場合の取得原価は下のようになります。
80,000円(累計購入金額)/5BTC(仮想通貨取得数)=16,000円(1BTC当たり取得原価)
売却価格の合計は、3BTCで48,000円となります。
なので、65,000円-18,000円×3=17,000円が利益となり、年末の保有仮想通貨は2BTC(32,000円)となります。
総収入金額:65,000円
必要経費:16,000円(1BTC当たり取得原価)×3(売却BTC数)=48,000円
雑所得:65,000円-48,000円=17,000円
保有仮想通貨残高:2BTC(32,000円)
ケース5:複数回購入と複数回売却(移動平均法)
- 1/1、1BTCを10,000円で購入
- 3/5、2BTCを20,000円で購入
- 5/10、2BTCを40,000円で売却
- 9/15、1BTCを20,000円で購入
- 12/20、1BTCを25,000円で売却
- 12/31、1BTCを30,000円で購入
移動平均法とは、仮想通貨の売買がされるたびに取得原価を計算する方法なのです。
移動平均法で計算した場合の取得原価は下のようになります。
「5/10時点での取得原価」
30,000円(5/10までの累計購入金額)/3BTC(5/10までの仮想通貨保有数)=10,000円(1BTC当たり取得原価)
5/10時点の売却価格は2BTCで40,000円です。
なので、40,000円-10,000円×2=20,000円が利益になり、5/10時点での保有仮想通貨は1BTC(取得原価10,000円)となります。
「12/20時点での取得原価」
30,000円(12/20までの累計購入金額)/2BTC(12/10までの仮想通貨保有数)=15,000円(1BTC当たり取得原価)
12/20時点の売却価格は1BTCで25,000円です。
なので、25,000円-15,000円×1=10,000円が利益になり、12/20時点の保有仮想通貨は1BTC(取得原価15,000円)となります。
つまり、年間の利益は20,000円(5/10分利益)+10,000円(12/10分利益)=30,000円となり、年末の保有仮想通貨は2BTC(45,000円)となります。
総収入金額:65,000円
必要経費:{10,000円(1BTC当たり取得原価)×2(売却BTC数)}+{15,000円(1BTC当たり取得原価)×1(売却BTC数)}=35,000円
雑所得:65,000円-35,000円=20,000円
保有仮想通貨残高:2BTC(45,000円)
総平均法と移動平均法の使い分けについて
ケース4とケース5を比較した場合に、同じ取引をしていても総平均法を利用したケース4のほうが利益が少なくなっています。
ただし、すべての仮想通貨を売却した場合の利益は完全に一致します。
また税務上のルールで、総平均法を利用する場合は、翌年以降も継続して総平均法を利用し続けなけ出ればなりません。
仮想通貨の雑所得はサラリーマンの給与所得との総合課税でなので、給与所得の少ない年に仮想通貨の利益を多く計上したいところです。
なので、総平均法と移動平均法の両方で利益を計算し、将来のサラリーマンとしての収入なども考えて自分に合った計算方法を選ぶことが重要です。
ケース6:仮想通貨同士の交換
- 7/1、1BTCを日本円で購入しました。1BTC=100,000円
- 7/10、1BTCでイーサリアムを購入しました。1BTC=200,000円、1ETH=20,000円
- イーサリアム購入時に取引手数料として、0.005BTCかかった。(200,000円×0.005BTC=1,000円)がかかった。
ケース6では、ビットコイン購入時とイーサリアム購入時のビットコイン価格が変わっていることに注意が必要です。
ビットコインでイーサリアムを購入する際のビットコインの価格上昇分は、利益として考える必要があります。
一旦、ビットコインを日本円に売却し、イーサリアムを日本円で購入したかのように考えるとわかりやすいと思います。
まずビットコインの取得原価が100,000円、売却価格を200,000円と考え、差額が100,000円となります。
ここから、イーサリアム購入時の支払った手数料1,000円を引いた99,000円が利益となります。
また、ビットコインの売却価格が手元に残るイーサリアムの取得原価となるので、200,000円(ビットコイン売却価格)/10ETH=20,000円(1ETH当たり取得原価)となります。
総収入金額:200,000円
必要経費:100,000円(BTCの取得原価)+1,000円(取引手数料)=101,000円
雑所得:200,000円-101,000円=99,000円
保有仮想通貨残高:10ETH(200,000円)
ケース7:仮想通貨を自分のウォレットへ送金
- 10/1、1BTCを自分のCoincheck(コインチェック)のウォレットからBitFlyer(ビットフライヤー)のウォレットへ送金した。1BTC=10,000円
- この際に送金手数料として0.005BTCがかかった。
自分の口座間での単なる送金にはもちろん税金はかかりません。
しかし、送金の際に支払った送金手数料0.005BTCは経費とすることができます。
つまり、10,000円(10/1のBTCの時価)×0.005BTC(送金手数料)=50円が経費となります。
総収入金額:0円
必要経費:50円(送金手数料)
雑所得:0円-50円=▲50円
ケース8:仮想通貨で買い物をした
- 11/20、家電量販店で10万円のパソコンを0.5BTC支払って購入した。1BTC=200,000円
- 買い物で支払ったビットコインは11/1に1BTC=100,000で購入したものであった。
ケース8では、11/1に購入したビットコインで11/20にパソコンを購入していますが、この際のビットコイン価格の変動に注目する必要があります。
仮想通貨で買い物をするときは、仮想通貨の価格上昇分を利益として考えなくてはいけません。
まずビットコインの取得原価を、100,000円(11/1の購入金額)×0.5(支払いビットコイン数)=50,000円と考えます。
次に、ビットコイン売却金額を200,000円(11/20ビットコイン価格)×0.5(支払いビットコイン数)=100,000円と考えます。
なので、売却金額と取得原価の差額50,000円が利益となります。
総収入金額:100,000円
必要経費:500,000円
雑所得:100,000円-50,000円=50,000円
保有仮想通貨残高:0.5BTC(50,000円)
ケース9:仮想通貨を友達にプレゼントした
- 4/10、仮想通貨を始めた友人に1BTC=10,000円をプレゼントした。
- プレゼントしたビットコインは4/1に1BTC=8,000で購入したものでした。
ケース9では友人に対価なく仮想通貨をプレゼントしています。
友達にプレゼントした場合も売買した時と同じように税金がかかります。
ただで仮想通貨をあげたからと言って、プレゼント時の価格を0円と考えることは認められません。仮想通貨を時価で売った場合と同様に処理します。
仮想通貨の取得原価が8,000円、仮想通貨のプレゼント時の価格が10,000円なので、2,000円の利益が出ていると考えます。
総収入金額:10,000円
必要経費:8,000円
雑所得:10,000円-8,000円=2,000円
ちなみに仮想通貨を受けとった側も、仮想通貨の時価で受け取ったものと考えます。
プレゼントされた場合は、受け取った全額が利益となり税金がかかります。
ケース10:仮想通貨をハードフォークによって受け取った
- 4/1、ビットコインが分裂し、所有するビットコインに足して1:1の割合でビットコインキャッシュが付与された。
- 12/1、ハードフォークによって得たビットコインキャッシュを100,000円で売却した。
ケース10は、ハードフォークによって新たな仮想通貨を取得した場合です。
ハードフォークによって誕生した仮想通貨は、その時点では価値が存在しません。なので、取得価格は0円と考えます。
そのため売却価格全額が利益となるので、100,000円が利益となり100,000円全額に対して税金がかかります。
総収入金額:100,000円
必要経費:0円
雑所得:10,000円-0円=10,000円
ケース11:仮想通貨をエアドロップで受け取った(市場価格なし)
- 3/1、エアドロップによって仮想通貨を取得した。取得した仮想通貨は未上場であり、市場価格が存在しない。
- 10/1、エアドロップによって取得した仮想通貨が上場を果たした。
- 12/1、エアドロップによって得た仮想通貨を10,000円で売却した。
ケース11は、エアドロップで市場価格がない仮想通貨を取得した場合です。
この場合は、ハードフォークで入手したケースと同様に、取得時点では価値がないため取得価格が0円と考えます。
そのため売却価格全額が利益となるので、10,000円が利益となり10,000円全額に対して税金がかかります。
総収入金額:100,000円
必要経費:0円
雑所得:100,000円-0円=100,000円
ケース12:仮想通貨をエアドロップで受け取った(市場価格あり)
- 5/1、エアドロップによって仮想通貨を取得した。取得した仮想通貨の市場価格は50,000円であった。
ケース12は、エアドロップで市場価格のある仮想通貨を取得した場合です。
取得した時点で市場価格があるため、取得価格全額がそのまま利益となります。
エアドロップで市場価値がある仮想通貨を取得した場合には、売却しなくても利益が発生するため注意が必要です。
総収入金額:50,000円
必要経費:0円
雑所得:50,000円-0円=50,000円
海外取引所を利用した場合の税金計算
海外取引所を利用した場合の税金計算の方法を紹介します。
国内取引所を利用したケースの応用で理解できるので、基本的なことがよくわかっていない人は、「国内取引所を利用した場合の税金計算」を読んでみてください。
海外取引所を利用する場合は、ビットコインを基軸通貨のように取引を行うことが多いので注意が必要です。
海外取引所に興味はあるけど、まだ始めていないという人は下の記事も参考にしてみてください。
ケース13:海外取引所でアルトコインをビットコインで購入
- 2/1、国内取引所で1BTCを日本円で購入した。1BTC=900,000円
- 2/5、1BTCを海外仮想通貨取引所に送金した。1BTC=1,000,000円
- 2/10、1BTCでADA(カルダノ)を購入した。1BTC=1,100,000円
海外取引所でアルトコインをビットコインで購入したケースですが、国内取引所で行う仮想通貨同士の交換と同じように考えます。
なので、ビットコインでカルダノを購入する際のビットコインの価格上昇分は、利益として考える必要があります。
ビットコインの取得原価が900,000円、売却価格を1,100,000円と考え、利益は200,000となります。
また、ビットコインの売却価格1,100,000が手元に残りカルダノの取得原価となります。
総収入金額:1,100,000円
必要経費:900,000円(BTC取得原価)
雑所得:1,100,000円-900,000円=200,000円
保有仮想通貨残高:1,100,000(ADA取得原価)
ケース14:海外取引所でビットコインをテザーに避難させた場合
- 2/1、国内取引所で1BTC=900,000円を日本円で購入した。
- 2/5、1BTCを海外仮想通貨取引所に送金。1BTC=1,000,000
- 2/10、1BTCでUSDT(テザー)に避難させた。1BTC=1,100,000
ビットコインなどの仮想通貨は価格変動が大きく、円建てで見た場合に資産価値が大きく目減りしてしまう可能性があります。
国内取引所であれば、一旦日本円にしておくことができますが、海外取引所では日本円の取り扱いがないことが多いです。
そこで、USDT(テザー)などの法定通貨に連動した仮想通貨であるステーブルコインに一時的に避難させることがあります。
しかし、ステーブルコインへの非難もアルトコインへの交換と同様の処理をしなければなりません。
そこで、ビットコインの取得原価が900,000円、売却価格1,100,000円と考え、利益は200,000円となります。
またビットコインの売却価格1,100,000円がそのまま、USDT(テザー)の取得価格となるのも同じことです。
総収入金額:1,100,000円
必要経費:900,000円(BTC取得原価)
雑所得:1,100,000円-900,000円=200,000円
保有仮想通貨残高:1,100,000(USDT取得原価)
ケース15:海外取引所での複数回購入と複数回売却(総平均法)
- 1月1日、10LTCを1BTCで購入(1BTC=100,000円)
- 3月5日、20LTCを2BTC円で購入(1BTC=100,000円)
- 5月10日、20LTCを4BTC円で売却(1BTC=200,000円)
- 9月15日、10LTCを2BTC円で購入(1BTC=200,000円)
- 12月20日、10LTCを2.5BTC円で売却(1BTC=250,000円)
- 12月31日、10LTCを3BTC円で購入(1BTC=300,000円)
総平均法とは、1年間の購入金額の累計を取得した仮想通貨数で割り、1通貨当たりの取得原価を計算する方法です。
海外取引所の場合、ビットコインを基軸通貨として計算をするので、少し複雑になっています。
「1/1購入分の取得原価」
10LTC(LTC購入量)×0.1(対BTCのLTC単価)×100,000円(対円のBTC単価)=100,000円
「3/5購入分の取得原価」
20LTC(LTC購入量)×0.1(対BTCのLTC単価)×100,000円(対円のBTC単価)=200,000円
「9/15購入分の取得原価」
10LTC(LTC購入量)×0.2(対BTCのLTC単価)×200,000円(対円のBTC単価)=400,000円
「12/31購入分の取得原価」
10LTC(LTC購入量)×0.3(対BTCのLTC単価)×300,000円(対円のBTC単価)=900,000円
「年間の1LTC当たりの取得原価」
(100,000円+200,000円+400,000円+900,000円)/50LTC(年間の総購入数)=32,000円(1LTC当たり取得原価)
「5/10売却価格」
20LTC×0.2(対BTCのLTC単価)×200,000円(対円のBTC単価)=800,000円
「12/20売却価格」
10LTC×0.25(対BTCのLTC単価)×250,000円(対円のBTC単価)=625,000円
「年間の利益」
(800,000+625,000)-(32,000×30)=465,000円
年末時点の保有仮想通貨:20LTC(取得原価6,400,000)
総収入金額:800,000円+625,000円=1,425,000円
必要経費:32,000×30=960,000円
雑所得:1,425,000円-960,000円=465,000円
保有仮想通貨残高:20LTC(640,000円)
ケース16:海外取引所での複数回購入と複数回売却(移動平均法)
- 1月1日、10LTCを1BTCで購入(1BTC=100,000円)
- 3月5日、20LTCを2BTC円で購入(1BTC=100,000円)
- 5月10日、20LTCを4BTC円で売却(1BTC=200,000円)
- 9月15日、10LTCを2BTC円で購入(1BTC=200,000円)
- 12月20日、10LTCを2.5BTC円で売却(1BTC=250,000円)
- 12月31日、10LTCを3BTC円で購入(1BTC=300,000円)
移動平均法とは、仮想通貨の売買がされるたびに取得原価を計算する方法なのです。
海外取引所の場合、ビットコインを基軸通貨として計算をするので、少し複雑になっています。
「1/1購入分の取得原価」
10LTC(LTC購入量)×0.1(対BTCのLTC単価)×100,000円(対円のBTC単価)=
100,000円
「3/5購入分の取得原価」
20LTC(LTC購入量)×0.1(対BTCのLTC単価)×100,000円(対円のBTC単価)=
200,000円
「5月10日時点での売却金額」
20LTC×0.2(対BTCのLTC単価)×200,000円(対円のBTC単価)=800,000円
「5/10売却分の取得原価」
(100,000円+200,000円)×(20/30)=200,000円
「5/10時点での利益」
800,000(売却金額)-200,000(取得原価)=600,000円
「9/15購入分の取得原価」
10LTC(LTC購入量)×0.2(対BTCのLTC単価)×200,000円(対円のBTC単価)=
400,000円
「12/20売却分の売却価格」
10LTC×0.25(対BTCのLTC単価)×250,000円(対円のBTC単価)=625,000円
「12/20売却分の取得原価」
(100,000円+400,000円)×(10/20)=250,000円
「12/20売却時利益」
625,000円-250,000円=375,000円
「12/31購入分の取得原価」
10LTC(LTC購入量)×0.3(対BTCのLTC単価)×300,000円(対円のBTC単価)=900,000円
「年間の利益」
600,000円+375,000円=975,000円
年末時点の保有仮想通貨:20LTC(取得原価1,150,000)
総収入金額:800,000円+625,000円=1,425,000円
必要経費:200,000円+250,000=450,000円
雑所得:1,425,000円-450,000円=975,000円
保有仮想通貨残高:20LTC(1,150,000円)
海外取引所を利用した場合の計算の困難さ
ケース14・15では海外取引所を利用した場合の税金計算について紹介しました。
わずか数回の取引でも、自分で計算を使用とするとかなり手間がかかるのがわかっていただけたと思います。
実際には取引回数がもっと多くなり、売買をする仮想通貨の種類も増えることになります。
また、仮想通貨取引の結果を確定申告する際には、必ず日本円で評価する必要があります。
その際にどこの取引所のレートで日本円に換算すればいいかですが、これも厳密に決まりがあるわけではありません。
これらの問題を個人の力で解決することは難しいといってしまっても過言ではありません。
「意図しない脱税」をおこなってしまわないためにも、実際に納税する際にはクリプタクトなどの自動損計算ツールを使うことをおすすめします。
外部リンク参考:クリプタクト
仮想通貨FXを利用した場合の税金計算
日本で人気の高いFXですが、仮想通貨でも行うことができます。
ここでは、仮想通貨でFXをおこなった場合にかかってくる税金について、ケースごとに紹介していきます。
仮想通貨FXに興味はあるけど、まだ始めていないという人は下の記事も参考にしてみてください。
ケース16:証拠金口座へ資金を移動した場合
- 5/1、FXをするために証拠金口座へ1,000,000を移した。
国内取引所で日本円を取引所の証拠金口座へ資金移動させたケースです。
単なる資金移動資金移動を行っただけなので、税金に影響することはありません。
総収入金額:0円
必要経費:0円
雑所得:0円
ケース17:国内取引所でFXトレードをした場合
- 5/10、1BTC=500,000円のときに売りポジションを2BTC保有した。
- 5/20、1BTC=250,000円のときに売りポジションをクローズし利益が確定した。この際にスワップ手数料として4,000円がかかった。
FXではポジションをクローズしたタイミングで損益を認識します。
また、売り・買いどちらのポジションから入ったとしても税金には影響はありません。
ここでは、5/20に売りポジションをクローズしたタイミングで、500,000円の利益が確定します。また4,000円のスワップ手数料は経費となります。
総収入金額:500,000円
必要経費:4,000円
雑所得:500,000円-4,000円=496,000円
ケース18:海外取引所でFXトレードをした場合
- 6/1、国内取引所でBTCを購入し、その日のうちに海外取引所の証拠金口座に5BTCを移した。1BTC=500,000円
- 6/10、1BTC=6,000ドルのときに買いポジションを2BTC保有した。
- 6/20、1BTC=9,000ドルのときに買いポジションをクローズして利益を確定した。1ドル=110円
- その結果、証拠金口座に0.5BTCが増えた。
- 6/30、証拠金口座の5.5BTCを国内取引所に移し日本円に交換した。1BTC=1,000,000円
ケース18では、2つのタイミングでの利益について考えます。
1つ目が海外取引所でのFXに関する利益です。
6/20に買いポジションをクローズしたタイミングで、0.5BTC×(9,000-6,000)×110円=660,000円が利益となります。
2つ目がビットコインを日本円に交換した際の利益です。
6/30に5.5BTCを日本円に交換したタイミングで、5.5BTC×1,000,000円-(2,500,000(BTC取得原価)+660,000(FXによる利益))=2,340,000円の利益となります。
総収入金額:660,000円+5,500,000円=6,160,000円
必要経費:2,500,000円+660,000円=3,160,000円
雑所得:6,160,000円-3,160,000円=3,000,000円
ケース19:FXでロスカットを受けた場合
- 8/1、取引所の証拠金口座に1,000,000円を入金した。
- 8/5、1BTC=500,000円のときに2BTCの売りポジションを保有した。
- 8/10、ビットコイン価格が高騰し1BTC=1,000,000円となったので、売りポジションが強制的にロスカットされてしまった。
ロスカットによりFXの取引が強制的に終了した場合でも、結論としては通常のFX取引と同じように処理をします。
なので8/10に売りポジションをクローズした場合と同じように考えるので、1,000,000円の損失が確定します。
総収入金額:-1,000,000円
必要経費:0円
雑所得:-1,000,000円-0円=-1,000,000円
FX取引の申告方法について
FX取引では多くの取引をするので、すべてを上記のように1つずつ計算していくのは現実的ではありません。
ここでも「海外取引所を利用した場合の計算の困難さ」でも紹介したように、自動損益計算ツールを使うことをおすすめします。
外部リンク参考:クリプタクト
その他の仮想通貨に関係する税金計算
ここからは、一般的な売買とは少し異なる仮想通貨に関係する税金の計算を紹介します。
レンディング・マイニング・ICOを始めてみようと思っている人などは、事前に確認してみてください。
セルフGOXに関しても紹介しているので、既にセルフGOXしてしまった人も是非読んでみてください。
ケース19:仮想通貨レンディングをおこなった場合
- 1/1、保有している1BTCを年利3%でレンディングした。1BTC=1,000,000
- 12/31、レンディングが満期となり、元本・利息を合わせて1.03BTCが返却された。1BTC=1,200,000
レンディングの場合では、元金の預け入れや返金については損益に影響はありません。
一方で、金利部分については利益として認識し、税金に関係してきます。
利息は受け取ったタイミングの時価で評価します。
0.03BTC(受取利息分)×1,200,000円(12/31のBTC価格)=36,000円
総収入金額:36,000円
必要経費:0円
雑所得:36,000円-0円=36,000円
ケース20:レンディングした仮想通貨が戻ってこなかった
- 7/1、保有している仮想通貨1BTCを年利25%でレンディングした。1BTC=1,000,000円
- 9/30、レンディングしたBTCが返却されない旨の連絡があった。1BTC=1,200,000
レンディングで貸し付けた仮想通貨が返ってこない場合は、貸し倒れ損失として預けたタイミングの時価で損失を評価します。
なので、貸し倒れ損失は1,000,000円となります。
ただし、貸し倒れ損失とするには以下のような条件が必要です。
・本当に帰ってくる見込みはないのか?
・全額返済されないのか?
・何度も問い合わせした記録があるか?
これらをしっかりと税務署に説明する必要があります。
大きな金額の貸し倒れ損失を計上する場合には、必ず税理士などの「専門家」に相談することをおすすめします。
総収入金額:0円
必要経費:1,000,000円(貸倒損失)
雑所得:0円-1,000,000円=▲1,000,000円
ケース21:仮想通貨マイニングをおこなった
- 4/1、マイニング用に90,000円のPCを購入した
- 9/30、マイニング報酬として、0.3BTCを得た。1BTC=1,000,000円
- 4/1~9/30までの6か月間、毎月25,000円の電気代がかかった。
マイニングによる収益は、マイニングで得たビットコインであり、経費は電気代や通信費、マイニングPC代などになります。
マイニングではビットコインを受け取ったタイミングで利益が発生します。日本円に換金した場合ではないので注意が必要です。
つまり、0.3BTC×1,000,000(9/30のBTC時価)-90,000(PC代)-25,000×6(マイニング期間の電気代)=60,000円
マイニング用PCの税務処理について
マイニング用PCを経費処理する場合には注意が必要です。
10万円以上のPCについては、全額を一度に経費とすることは原則できません。
使える期間に応じて経費とすることが決められているので、PCの場合には4年間に分けて経費にする必要があります。
クラウドマイニングの経費について
クラウドマイニングとは自分でPCを持つのではなく、大規模にマイニングをおこなっている会社などが保有するハッシュレート(PCの計算能力)を購入するというものです。
クラウドマイニングでは、自分でPCを持たずに業者が行ったマイニングの結果を購入したハッシュレートに従って受け取る仕組みです。
PCを自分で持たないので、PC代や電気代を経費とすることはできませんが、ハッシュレートの購入代金を経費とできます。
その経費は、契約期間に従って計上する期間が変わってきます。
・1年未満の契約の場合、支払い時に一括で経費として処理する。
・1年以上の契約期間がある場合、期間で按分して経費として処理する。
・無期契約の場合、5年の期間で按分する。(ただし、20万円未満の経費を一括計上)
ステーキング報酬を得た場合
マイニングと同じようなシステムとしてステーキングがあります。
ステーキングでもマイニングと同様に、報酬を受け取ったタイミングで収益が発生します。
ただし、ステーキングでは仮想通貨をもっているだけでステーキング報酬が得られるので、ほとんど経費とできるものがありません。
報酬がほとんどの場合にそのまま全額利益になります。
ケース22:ビットコインでICOトークンを購入した
- 3/1、1BTCを日本円で購入しました。1BTC=800,000円
- 3/10、ICO投資のために、1BTCで10ICOトークンを購入した。1BTC=900,000円であった。
ICOトークンのプレセールに参加した場合、ビットコインで購入することが一般的です。
ICOトークンの購入については、アルトコインとの交換と同じように、ビットコインの購入価格とICOトークン購入時点のビットコイン価格の差額が利益となります。
なので、900,000円-800,000円=100,000円がICOトークン購入時点での利益となります。
また、ICOトークンの取得原価は3/10時点のビットコイン価格となるので、900,000円となります。
総収入金額:900,000円
必要経費:800,000円
雑所得:900,000円-800,000円=100,000円
保有仮想通貨残高:10ICOトークン(900,000円)
ケース23:ICOトークンが上場したので売却した
- 9/1、ケース22で購入したICOトークンが上場した。1ICOトークン=0.4BTC
- 9/10、ICOトークンをすべてビットコインに交換した。1ICOトークン=0.5BTC、1BTC=1,000,000円
購入したICOトークンが無事上場を果たした場合に、それをビットコインに交換したタイミングで利益が発生することに注意が必要です。
10ICOトークン×0.5(交換時の対BTCレート)×1,000,000円(交換時のBTCの対日本円レート)-900,000(ICOトークン取得原価)=4,100,000円が利益となります。
総収入金額:5,000,000円(ICOトークン売却価格)
必要経費:900,000円(ICOトークン取得原価)
雑所得:5,000,000円-900,000円=4,100,000円
ICOトークンが上場しなかった場合は?
結論として、ICOトークンが上場しなかった場合は、利益とも損失ともできません。
開発元から「IOCトークンはもう上場することはなくなりました。」と連絡がくれば、損失とすることができるかもしれませんが、このような連絡は基本的にはありません。
詐欺的なICOであった場合も、同じように損失とすることは難しいです。
ICOにはこういったリスクがつきものなので、注意が必要です。
ケース24:仮想通貨をセルフGOXしてしまった
- 4/1、10BTCを送金しようとしたときに、送金先を間違えてしまい復元不可能となってしまった。
いわゆるセルフゴックスといわれる、自分の手で仮想通貨を紛失しまった場合です。
セルフGOXはm現在の税法で個別のルールがないために、損失とすることさえできません。
ICOトークンが上場できなかった場合と同様に、ルールがしっかりと整備される日を待つしかありません。
総収入金額:0円
必要経費:0円
雑所得:0円
サラリーマンのための確定申告書の作り方

会社員の人の多くは、年末調整をしたことがあっても確定申告はしたことがないという人が多いのではないでしょうか?
始めて確定申告をする人のために、サラリーマンの一般的なケースについて紹介していきます。
ただし注意してほしいのは、複雑な確定申告が必要な場合、仮想通貨による利益がかなり大きな額になる場合には、必ず税理士などの「専門家」に相談したうえで、確定申告を行って下さい。
専門家に相談することで、問題が起こった場合にも対応ができます。
結果的に安上がりになることもあるので、大きな利益を得た人は専門家に相談することを心からおすすめします。
確定申告のスケジュール
所得税の確定申告期間は、2/16~3/15までになっています。
2020年1/1~12/31までに得た所得については、2021年2/16~3/15までに確定申告を行い、3/15までに納税しなければなりません。
所得税と復興特別所得税については、銀行口座からの振替納税が認められています。
振替日は2021年4/19となるので、当日までに口座残高をしっかりと確認しておきましょう。
実際の確定申告の手順
では、実際の確定申告の手順を紹介していきます。
まず会社から受け取っている源泉徴収票と仮想通貨取引所で確認できる仮想通貨取引履歴を準備してください。
書類の準備ができたら、あとは下の国税庁のサイトから順番に入力していけば大丈夫です。
【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp)
今回は事前準備のいらない「印刷して提出」する方法を紹介します。
サイトの指示に従えば、難しいことはありません。
少しだけややこしところは解説を入れていきます。
- まずは作成開始を選んでください。

- その次に「印刷して提出」を選び、利用規約に同意したらスタートです。

- 今回確定申告を行う年を選ぶので、令和2年分から所得税を選択してください。

- 自分の生年月日を入力します。
- 申告に関する1つ目の質問は仮想通貨による収入があるので、「はい」を選択します。
- 一般のサラリーマンは青色申告や予定納税をおこなっていないので、2つ目と3つ目は両方とも「いいえ」を選択します。

- 次に収入金額・所得金額の入力を行います。
- 今回は、サラリーマンとしての「給与所得」と仮想通貨による「雑所得」について入力していきます。

- サラリーマンは会社で年末調整がされているので、「書面で交付された年末調整済みの源泉調整票の入力」から入力します。

- 指示通り、源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収額」を転記し、扶養家族の有無、「社会保険料等の金額」も記入して下さい。
- その他の転記箇所もかなり詳しく説明されているので、その通り従って入力すれば大丈夫です。

- 雑(その他)所得の入力については詳しく見ていきましょう。
- 「種目」は、暗号資産を選択してください。
- 業務に該当するかは、仮想通貨取引の場合は「いいえ」を選びます。
- 「収入金額」は、仮想通貨の売却金額合計を記入します。
- 「必要経費」は、仮想通貨の取得原価や仮想通貨の取引手数料、関係する書籍代、PC代などの合計金額を入力してください。
- 「源泉徴収税額」は、仮想通貨取引で源泉徴収されることは、ほぼないで0円でいいかと思います。
- 「所得の生ずる場所」「報酬などの支払者の氏名・名称」は自分がメインで使っている取引所を書いておきましょう。

- 次に進むと、給与所得を入力したのときの所得控除の金額が表示されます。
- 改めて金額に間違いがないか、入力すべき控除がないか確認したら次に進んでください。

- 税額控除については、仮想通貨取引では関係ありません。
- 仮想通貨とは別に何か入力する必要がある人はここで入力しておきましょう。

- 計算結果確認では、自分が納付すべき金額が表示されています。

- 後は納税方法を選択します。
- 振替納税・コンビニQR納付・電子納付・クレジットカード納付・窓口納付から選ぶことができます。
- 最後に、住所と氏名などの入力を済ませませると、下のような確定申告書が出来上がります。
- 印刷して、本人確認書類と一緒に、税務署へ送付するか、税務署にもっていけば完了です。

サラリーマンの確定申告と税金計算まとめ
今回は、サラリーマンに向けた確定申告と税金計算にについてまとめてみました。
税金計算については、できる限りすべてを網羅できるようにかなりたくさんのケーススタディを用意してみました。
確定申告では、実際の国税庁のサイトの画像を使って初めての人でもわかりやすく紹介したつもりです。
いかがでしたでしょうか?

正直に言ってかなり時間をかけてしまいました。
でも、税金は仮想通貨投資とは切っても切れない関係にあります。
少しでも、税金を身近に感じてもらえたら嬉しいです。
「こんな場合はどうなるの?」そんな疑問があれば、ぜひコメントしてください。
随時、情報を更新していこうと思っているので、時折このページを見に戻ってきてもらえると嬉しいです。
なお、海外の取引所では、残念ながら詐欺や出金拒否などが頻発しています。
何も分からない状態からトレードを初めて、資金が10倍になった!と喜んでいたら出金拒否。
そのまま資金がなくなってしまうなんていう事もあります。
私もまだ取引を始めたばかりの頃は、苦い経験をしてきました。
自分の失敗を無駄にしないためにも、せめてこのサイトの読者だけでも勝って欲しい!のです。
そこで、弊メディアでは初心者向けに、海外仮想通貨や海外FXをマスターするためのロードマップを用意しました。
ぜひご覧下さい↓